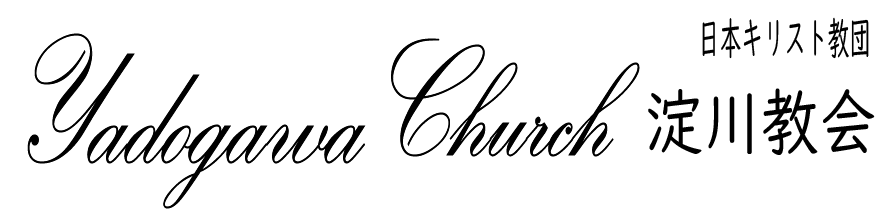大祭司イエス
「ところが実際は、世の終わりにただ一度、御自身をいけにえとして献げて罪を取り去るために、現れてくださいました」。 ヘブライ書9.23-28

罪は聖書の中心となる言葉で、旧約、新約問わず一貫しています。それは「的はずれ」ということで、弓で矢を射るとき的をはずすという意味です(詩編78.57)。造られた人間が創造者である神のようになり、絶対者のように振る舞う。罪とは人を傷つけたり、人と争ったりすることだけではなく、また法を犯すことだけでもなく、もっと根本的なところではこのように人間が自分の立場を間違えて、神のようになろうとするところにあります。神中心でなく、自分中心、人間中心、自己絶対化です。
夏目漱石の小説に「三四郎」があります。新聞の連載になったような一般向きの小説で、今も依然として人気があります。彼の小説の中には陰に陽に聖書の言葉や考えが出てきます。「われはわが咎(とが)を知る。わが罪は常にわが前にあり」。これは詩編51.5の文語訳の言葉で、今の聖書では「わたしの罪は常にわたしの前に置かれています」となっています。東京・本郷にある教会の礼拝に出席した帰り、美禰子(三四郎が好きだった女性)は三四郎にこの言葉を語りました。美禰子も三四郎に好意を寄せていたのですが、結局は他の男と結婚することになりました。その場面で、聞き取れないくらい小さな声で美禰子がこの聖書の言葉を言いました。しかし三四郎はそれを明らかに聞き取ったと書かれています。この場合、美禰子にとって「わが罪」とは何を指しているのだろうか、改めて考えてみました。三四郎の自分に対する気持ちを知っていながら他の男のもとへ嫁ぐ自分の身勝手さと、三四郎への裏切りをいっているのだろうか。あるいは自分も三四郎を好きだったのに、その気持ちを大切にできなかった自分の心に対する裏切りであるようにも聞こえます。さらには世間の関わりの中では、自分の気持ちだけではどうすることもできないという思いが、この罪という言葉で表現されているのだろうか。
旧約時代の大祭司が年に一度聖所の奥にある至聖所に入って、動物をいけにえとして献げ、その血によって民のもろもろの罪を贖っていました。それに対して、イエス・キリストは動物の血ではなく御自身の尊い血潮、それは神の独り子として流された血によって人々の罪を贖われました。それゆえもはや毎年行う必要はなく、ただ一度だけ流されることによってわたしたちの罪を贖うことができました。だからこそイエスは大祭司でした。それこそが大祭司としての働きであり、旧約時代を踏襲しながらも、それをはるかに超えた永遠の救い主としてわたしたちを導き、いやすことができたのです。まさに「この大祭司は、わたしたちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において、わたしたちと同様に試練に遭われたのです」(4.15)といわれる方なのです。人間は、またこの世界は、今も神に敵対し、隣人に敵対し、さらにはそのことで自分自身にも敵対しています。まことにわたしたちは失われた者なのです。しかしこの大祭司なるイエス・キリストの豊かな罪の贖いによっていやされたのですから、わたしたちはこの主を信じ、この主に導かれながら歩むことが今もゆるされているのです。(高橋牧師記)